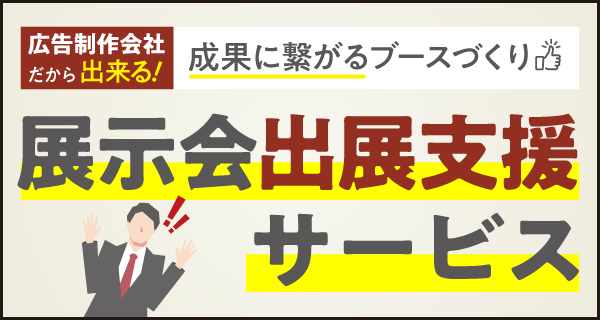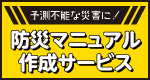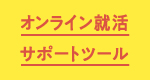夜明け前(下)
相変わらず、春の雨は静かに降り続いている。雨脚は強まることも、弱まることもなく、道路に平坦なリズムを刻んでいく。私は雨傘を右手から左手に持ち替えた。その時、少しの雨粒が路に横たわる男にこぼれ落ちた。しかし、それは男にとって大きな問題ではなかった。私はあらためて、地面に突っ伏したままの男をまじまじと見つめた。汚い、汚れている、と確信した。雨に濡れているからではない。いわゆる住所不定者と思わしき風体を、男の表情や着衣から感じ取っていたのだ。
「腰が痛くて動けない。起こして…」。
倒れていた男は私に懇願するように言った。
私は、逡巡した。
助けたい気持ちは、もちろんある。しかし、手を伸ばせなかった。触れたくない、濡れたくないという感情が勝っていたのだ。
私は男の声が届いてないふりをして、白々しく「そろそろ救急車が来るころだが」と、独り言というには大きすぎる声でつぶやきながら、救急車が来ると思われる方へ走った。一人の下衆な英雄は、自身の背中に2つの視線が突き刺さっていることを感じとっていた。
間もなく、救急車のサイレンが聞こえてきた。私は重たい沈黙を切り裂くように、開いたままの傘を天に掲げ、大きな身振りで救急車に合図を送り、倒れたままの男に「救急車が来ましたから。安心してください」と、なおも親切心を押し売った。そして、ほぼ同時刻に到着した警察官に運転手を引き合わせ、正義面で現場検証に立ち会った。若い警察官は恐縮しながら、何度も私に対して感謝の意を述べる。一通り質問に答え、連絡先を伝えると、ようやく「事故」から解放された。私は現場を顧みることなく、自家用車を停めていた駐車場に向かって足早に歩いた。とにかく、私は帰りたい一心だったのだ。
エンジンを始動させ、いつも以上に注意深く周囲を確認し、静かに発進した。入り組んだ細い路地を抜けると、見通しの良い大通りに出る。3つ先の信号機が青から赤に変わり、連動するように、さらにその先の信号も色を変えていくのが分かった。私は暗闇に浮かぶ青と赤の光に誘われるようにアクセルを強く踏み込んだ。交差点に灯る色など、どちらでも良かった。
私の黒い塊は、白みはじめた空に覆われ、どこかへ隠れていった。それが、どこなのかは私にはわからない。自宅に戻り、車のエンジンを切ると、私は運転席に携帯電話を置いたまま、車のドアを閉めた。