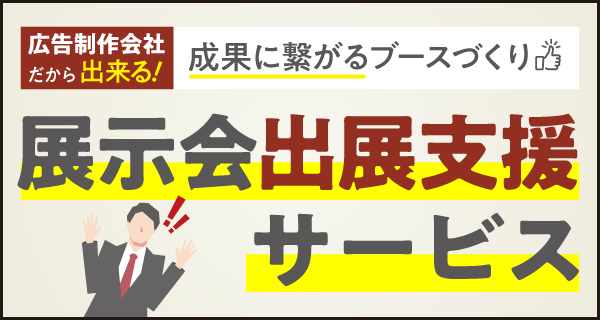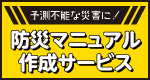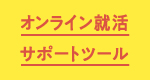夜明け前(上)
仲田路はすべて街の中である。あるところは店員のダミ声が響き渡る焼き鳥屋であり、またあるところは安さが自慢の理髪店である。これらと対峙するように私たちの事務所が建つ。一筋の路はこの街を貫いていた。通称、仲田銀座である。
4月の終わり、夜も明けようかというころ。ようやく残業を終えた私は一人とぼとぼと仲田銀座をくだっていた。春の冷たい雨は静かに、一定の間隔で私の傘を叩く。疲れ切っていた私はぼんやりと両肩を下げ、漆黒の中、雨にかすむ信号の赤を何とか認めた、まさにその瞬間のことであった。
私の目の端で自動車と自転車の接触事故が起こった。自転車に乗った男は道路にはじき飛ばされ、まるで演劇のように街灯の真下に身体を横たえた。黄色い明かりに照らされた男は、ひどく汚れていた、ように見えた。冷たい雨が容赦なく男に降り注ぐ。一歩二歩、近づく。男が動く様子はない。私は意を決し、大きな声で「大丈夫ですか?」と叫びながら、男に近づいた。すると、男は小さなうめき声をあげた。どうやら、息はあるようだ。出血も認められない。私は開いていた傘を男の上に掲げ、同時に携帯電話を取り出し、人生で初めての119番を押した。救急隊員に場所を知らせながら、濡れたアスファルトに横たわる男を眺め、傘を差しだしても意味が無いよな、などと考えていた。私は自分でも驚くほど冷静だった。
一方、自動車の運転手は呆然と佇むばかりだった。人間が自分を見失うとは、まさにこのことなのだと感じた。運転手は30歳前後、小綺麗な身なりをしたサラリーマンだった。自動車のボディには赤と青な派手な模様、さらに社名が大書され、一目で営業車とわかった。私は運転手に、速やかに自動車を道路の端に寄せるよう、強い口調で指示した。運転手は何も言わず、ただ小さくうなずき、言われた通りに自動車を動かした。運転手からはアルコールの匂いが漂っていた。